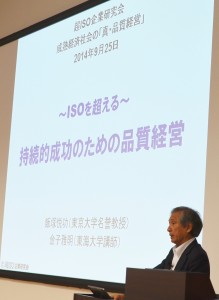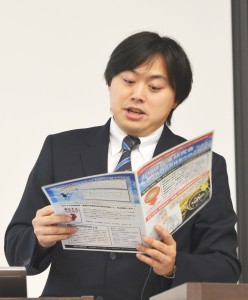9/25開催フォーラムの記事(第1部基調講演)
2014.10.14
9月25日、東海大学高輪キャンパスにて超ISO企業研究会フォーラムを開催いたしました。当日は台風の影響による悪天候の中、100名を超える方々にご来場いただき、皆様真剣にお聞きいただきました。
第1部基調講演、第2部パネルディスカッションと2部構成での開催、まずは、第1部についてそのエッセンスをお届けします。
第1部 基調講演
第1部では、超ISO企業研究会会長の飯塚悦功教授と副会長の金子雅明先生による基調講演として、真の品質経営のあり方と、品質経営実践ツールの概要説明を行いました。
超ISO企業研究会会長・東京大学名誉教授 飯塚悦功
■ 成熟経済社会のおける品質経営のあり方
品質に関する国際規格であるISO9001が発表されてから27年がたち、同規格を取得しているだけでは品質のプロとは言えない時代になったと思います。そこで、企業がもう一度品質に向き合い、改めて品質経営をテコにした持続的な成長をしてほしいという想いから、超ISO企業研究会を発足しました。今回のフォーラムでは品質経営が企業にどのようなメリットをもたらすかをお伝えできればと思います。
先立って私からお話しするテーマは「成熟経済社会における品質経営のあり方」です。成熟した現在の経済社会において、品質経営はどのようにあるべきなのかをお話しようと思います。
まず前提として、企業は製品・サービスを通して顧客に「価値」を提供するために存在していると定義します。そこで得た利益はあくまでも「価値」の結果であり、また新たな価値生産をするための原資にすぎません。真の品質経営は、顧客の求める「価値」をどのように提供していくかを考えるモデルとなります。
しかし、成熟経済社会の変化のスピードは非常に早く、企業に求められる「価値」もどんどん変わっていきます。企業にはいま、顧客のニーズがどのように変わっていくかを見定めるセンスと、そこに自社を適応させ、「価値」を継続的に産み出せる能力が問われているのです。
こうした状況下においては、企業はまず自社の「強み」を知る必要があります。顧客や競合に対して自分がどのような「強み」を持っているか理解したうえで、それをどのように時代にマッチングさせるかを考えなければいけません。日本経済はしばらく落ち込んでいましたが、そのなかでも変化に適応した優れた企業はいくつもあります。それらの企業は揺るぎない「価値」や「強み」を持っており、それを時代に適応させることができたから生き残ることができたのでしょう。
その一方で、成熟経済社会においては、営業力、企画力、開発力、その全てを「強み」にする必要はないと考えます。自社のコアコンピタンス(=競合優位性)を見つけて、そこに資源を集中することが大切なのです。恐らくこれまで変化に対応してきた全ての企業が、コアコンピタンスを重要視していたのだと思います。
成熟経済社会において持続的な成功をおさめるためには、まず自社の強みを理解し、そのうえで時代の変化を先読みし、ときに自分も変化させ、それをシステム化していくことが求められているのです。
11月末には(事務局 注:発行は12/20の予定に現在なっています)、こうした新たな持続的成功モデルを示したJIS9005という規格をリリースできると思いますが、多くの企業がこのような品質経営の仕組みをテコにして、持続的成長を遂げられることを願っています。
超ISO企業研究会副会長・東海大学講師 金子雅明
■ QMS(クオリティマネジメントシステム)構築のための4つの条件
企業が持続的に成功するためのQMSを設計するには、以下4つの条件を全て把握する必要があります。
当研究会では、QMS(クオリティマネジメントシステム=品質管理システム)を戦略的に設計するための品質経営実践ツールを制作しています。このツールは4つのモジュールに分かれており、実際に企業へコンサルティングする際には全てのモジュールを理解・活用してもらっています。今回はこの4つのモジュールに取り組む前段階として、基本的なQMSの設計の考え方をお話します。
飯塚先生から話がありました品質経営モデルの背景をふまえて、私からはそのシステムをどのように構築していくかという話をしたいと思います。
①顧客価値
②競争優位
③システム化
④変化
条件1:顧客価値
企業が製品を顧客におさめると、顧客はどのような価値を得られるか。この考え方を「顧客価値」と呼んでおり、QMSを始めるにあたり、まずはこれを考えてもらっています。「価値」と聞くとどうしても製品の機能について述べてしまいがちですが、ここでは機能自体ではなく、その機能を提供した結果、顧客がどのようなメリットを得られたかを考える必要があります。たとえばスターバックスなら提供しているのは「コーヒー」ではなく、「自宅でも会社でもない、ホッとできる場所・時間」といった具合です。QMSを設計する際に、このように自社の提供する価値が何なのかを明確にすることが大切であり、多くの企業がこの答えを出すことにかなりの時間を費やしています。
条件2:競争優位
顧客価値がわかると企業はその価値を活かしてどのように成長すべきかも考えられるようになるのですが、どの業界にも必ず競合はいますので、競合に勝つための要素も考えなければなりません。私達は競合に勝つための要素を「競争優位」と呼んでいます。競争力を持った価値を顧客に提供するためには、競合にはない「能力」が必要となるので、自社と競合を比較した際に優位になる特徴・能力を考えることを重要視しています。
条件3:システム化
条件1、2で考えた価値や能力を日常的に発揮できるようにすることを「システム化」と呼びます。企業が持続的に成長していくために必要なことは、競争優位性の高い顧客価値をいつでも、どこでも、誰でも発揮できる環境をつくることです。特定の人物に依存していたり、ある時期だけしか価値を提供できないような環境ではなく、誰でもどんな状況でも価値を提供できる環境を持続できるシステムが必要なのです。11月末にリリースされるJIS9005にも、自社の能力をシステム化する仕組みを取り入れていますが、企業が継続的な成長を続けるうえで「システム化」は不可欠なものなのです。
条件4:変化
システム化ができていれば基本的に自社の競争優位は保たれることになりますが、外部環境が変わるとそれも崩れることがあります。このように、これまで保たれていた環境が変わることをここでは「変化」と定義しています。QMSでは、「変化」への対応もシステムに落とし込むことで、イノベーションさえもマネジメントできると考えています。ここでいう「変化」には協力会社との関係性や、競合会社の増減、顧客の状況のほかにも、人口の増減、政府の政策、文化、価値観、地政学の変動も対象としています。これまで描いた顧客価値や競争優位のシナリオに対して、いま挙げた要素が変化するとどのような影響を受けるのかを想定することが、「変化」への考え方になります。
上記4つの条件を踏まえてQMSを設計し、継続的な成長を目指すのが真の品質経営の考え方です。詳細は実践ツールの4つのモジュールで落とし込むかたちとなりますので、もし興味がある方は相談していただければと思います。第2部では実際にツールを使って品質経営に取り組んでいる企業の方にも登壇いただいて、パネルディスカッションを行います。具体的な話はそちらを参考にしてください。